「アインシュタイン その生涯、研究、遺産」
原題:Einstein, The Man, the Genius, and the Theory
of Relativity
ドイツ語題:Einstein, Sein Leben, Sein Forschung,
Sein Vermächtnis
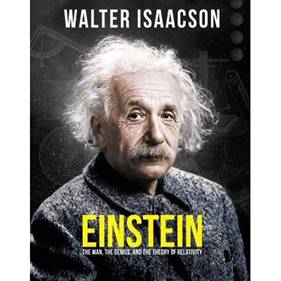
ウォルター・アイザクソン
Walter Isaacson
(2018年)
アメリカのジャーナリスト、ウォルター・アイザクソンの書いたアルベルト・アインシュタインの伝記である。最近、もっぱら小説を読んでいたので、たまには伝記でもと思って読み始めたが、これが意外に面白く、「はまって」しまった。アインシュタインの生涯、業績、時代背景が短い単位で上手くミックスされ、専門的になり過ぎず、気軽に読めるスタイルに仕上がっている。
通常、私の書評のスタイルは、ストーリーを紹介し、最後にまとめて感想を書くのを常としている。しかし、今回は、伝記ということで、ストーリーが追えない。それで、本の内容に触れつつ、自分の感想を混ぜていくことにする。
アインシュタインの出現前。
十九世紀の終わりまでに、ガリレオ・ガリレイとアイザック・ニュートンにより、物理学の基礎は確立されていた。それに、マイケル・ファラデーの電磁波の法則を加え、世の中の森羅万象は、彼らの理論で一応説明できると考えられていた。アインシュタインの登場した時代は、そういう意味で、物理学が「落ち着いた」時代と言える。光は波であると考えられ、波が水を媒体にして伝わるように、光の波も媒体により伝わると考えられていた。「エーテル」と呼ばれるその媒体が宇宙空間を満たし、それが光の波を伝えているという説が、当時有力であった。しかし、その「エーテル」は、様々の人々の観測、実験によっても、まだ存在を確認されていなかった。アインシュタインは「落ち着いた」時代に彗星のごとく現れ、再び「波風を立てる」役目をする。
子供の頃のアインシュタイン
アインシュタインのような天才が、どんな子供であったか、大いに興味のあるところだ。
アルベルト・アインシュタインは一八七九年、ユダヤ人の商人の子供としてドイツのウルムに生まれる。言葉が遅く、心配した父親は、アルベルトを医者に見せたという。また家の使用人はアルベルトを「お馬鹿さん」と呼んでいたという。ここからは、私の意見であるが、「言葉で考える人」と「頭で考える人」がいると思う。「喋りながら思考を進めるタイプの人」、「思考を進めてからそれを言葉にするタイプの人」と言っても良い。アインシュタインは間違えなく後者である。「言葉が遅かった」ということが、かえって彼の思考能力を高めたと言えるのではないだろうか。
また、彼がユダヤ人であること、これはアインシュタインの将来を、大きく左右することになる。当時のドイツにおけるユダヤ人の立場は、現在の米国における黒人の立場と似ていると理解している。人種差別から這い上がることは、並大抵のことではなかったと思う。
アインシュタインは生涯「反骨の人」であった。権力への反発、既成概念対する疑いから、彼の全て始まっている。そして、その精神は、子供の頃から発揮されていたのだ。アインシュタインの物理学への興味の発端が、五歳のとき父親からプレゼントされた「コンパス」つまり「方位磁石」であるというのも面白い。また、アインシュタインはバイオリンを習い、その演奏が彼の「生涯の趣味」になった。特にモーツァルトの音楽が好きだった。
「ベートーベンは作為的だが、モーツァルトは宇宙の法則をそのまま具現化したものだ。」と後年彼は述べている。物理学の世界を、音で表すとモーツァルトになるという発想が面白い。
学校
次に、天才は、どのような学校教育を受けたのか、果たして、彼は学校では超優秀な生徒だったのか、興味のあるところである。アインシュタイン一家はウルムから、ミュンヘンに移ったが、父親の事業の失敗で、一家は北イタリアに移ることになる。しかし、アルベルトだけは、ドイツで学校を終わらせるためにミュンヘンに残る。彼は権力に屈しない、悪く言えば教師の権威をないがしろにする、扱いにくい生徒だった。彼はそりの合わなかったドイツの学校を中退し、チューリヒの「ポリテクニク」(工科大学)を受験しようとする。しかし不合格となる。浪人中の一年間、スイスのアーラウという街で、ギムナジウムに通うことになる。そこの学校の独創性を大切にする教育で、ようやくアインシュタインの才能の花が開き始める、翌年、一八九六年に十七歳のアインシュタインは「ポリテクニク」を再度受験。合格する。
「ポリテクニク」、ほぼ大学と同じだが、卒業しても「ドクター」を名乗れず、研究者というよりも、教師を養成することを目的にしていると書かれている。「教育大学」のようなものだと思われる。しかし、そこでも、アインシュタインは、好きな科目には興味を示すが、特に、実験などには興味を示さず、その科目はひどい成績であったという。
アインシュタインからは「権威や権力に反発するティーンエージャー」という印象を受ける。そして、その「反発」これが、将来の物理学の根底を打ち破る発見のエネルギーになったことは間違いない。ただ、同じ天才でも野口英世のような浪費癖、奇行はなく、結構、「普通の人」だったことに、かえって驚いた。
最初の結婚
ポリテクニクに唯一の女子学生がいた。セルビア出身のミレヴァ・マリッチである。当時、女性が大学に入ること自体が異例中の異例だった。
「女子トイレはあったのだろうか。」
と要らない心配をしてしまう。ミレヴァは容姿もイマイチで、足も悪かったが、アインシュタインは彼女を好きになる。彼女との交際は、家族に、特に母親には大反対された。アインシュタインは卒業試験に合格するが、ミレヴァは落第する。休暇を一緒に過ごした二人だが、ミレヴァは妊娠してしまう。彼女は追試にも落ち、結果的に卒業を断念する。二人の間に出来た女の子は里子に出され、その存在は後年まで明らかにされなかった。ミレヴァはアインシュタインが論文を発表する上で、よき相談相手となったようだ。
二人は結婚することになるが、そのために、アインシュタインは職に就く必要があった。
「いつの時代も、結婚するとなると男には定職が求められる。」
私事だが、結婚のために留学を断念した。一九〇二年、彼は、スイス、ベルンの特許局に三等審査官として採用されることになる。「東京特許許可局」ではなく「ベルン特許許可局」。
彼の主な業績が、この特許局職員時代になされたものであるのは驚きに値する。彼は、フルタイムで働きながら、残されたわずかな時間を利用して、数多くの論文を書いたのである。しかし、アインシュタインが大学に学者として残らなかった方が、結果的に良かったと考える人も多いと、アイザクソンは書いている。大学にはびこる権威主義の中では、アインシュタインの自由な発想の芽が潰されていた可能性もある。ともかく、「特殊相対性理論」、「量子論」などの彼の主な業績は、特許局職員時代になされたものである。人間、何かが幸いするか分からないということも言えるかもしれないが、「どんな状況でも力を発揮できるのが、天才なのだ」とも言えるかも知れない。
奇跡の年
ベルンの特許局職員時代、アインシュタインは、「アカデミー・オリンピア」という勉強会を友人のコンラッド・ハブレヒト、モーリス・ソロヴィーネと開催していた。三人は、物理学のみならず、哲学や文学に関しても意見を交わした。
一九〇五年は、アインシュタインにとって「奇跡の年」と言われている、「量子論」と「特殊相対性理論」を相次いで発表したからである。実験など一切せず、紙と鉛筆と頭脳だけで、二十世紀の最大発見とも言えることを、短時間で成し遂げてしまったのは、驚嘆するのみ、正に「奇跡」である。アイザクソンの本では、両方の理論についてサラッと述べられているだけなので、私はYouTube等を使って、理論の説明を聞き、理解しようと努めた。そして、改めてその斬新さに気付いた。
量子論は、物質は極めて小さい粒子から成り立っているという考え。光も、これまで考えられていたような「波」ではなく、「粒子」であると、アインシュタインは主張した。現在は、物質は原子から成り立ち、原子は、原子核とその周りを回る電子から出来ていることは、誰もが知っている。量子論を調べてみて、改めて驚いたことがある。原子核を野球場の真ん中、ピッチャーマウンドの上にある針の穴の大きさと仮定すると、一番内側の電子は、野球場のフェンス際を回っているという。つまり、原子の中は極めてスカスカの世界なのだ。硬い金属の中も、実はスカスカの原子から成り立っているのが不思議な気がする。また、「波」だと考えられていた光も、粒子であると仮定している。
特殊相対性理論は、「光の速度は常に一定」というアインシュタインが立てた仮説を前提にすると、どんな世界が広がるかを描いている。平たく言うと、「相対的」に動いている物質の間では、時間の進み方が違ってくるというのである。そして「光より早い物質はあり得ない」ということもポイントだ。質量とエネルギーの関係式:E=mc²は余りにも有名である。
これらの理論、発表時に一大センセーションを巻き起こしたわけではない。最初は殆ど誰も注目していなかった。これらの理論は、後年実験によって確かめられることになるのだが、それは何年、いや何十年も先の話になる。それほど、アインシュタインの理論は、当時としては「ぶっ飛んでいた」のである。
大学へ
アインシュタインの論文は次第に知られるようになり、同調者も現れる。彼の理論に注目し、彼を訪ねた物理学者のマックス・フォン・ラウエは、アインシュタインが特許局の職員であることに驚く。そして、プラハ大学教授の職を斡旋する。アインシュタインもそれを受け、十年近く住んだベルンを離れプラハに家族で移住することになる。アルベルトとミレヴァの間には、その後二人の男の子が生まれていた。
しかし、妻のミレヴァはプラハでの生活に慣れることができなかった。彼女はうつ病を発症し、スイスに戻る。そんなとき、アルベルトの姪のエルザが離婚して家に戻って来る。彼女のことを昔から好きだったアインシュタインは、彼女と付き合い始める。しかし、その時点で、彼はミレヴァとの離婚は考えていなかった。しかし、エルザが病気になったアルベルトを献身的に介護したのをきっかけに、彼はミレヴァと別れ、エルザと結婚することを決意する。
世の中の天才と呼ばれる人は、常人では考えられない行動パターンを示すことが多いが、アインシュタインには、それが少ないように感じられる。同じく物理学を志した妻との離婚、姪との再婚等は、まあまあ、普通の人間として許される範囲だろう。時代は急激に変わり、一九一四年、第一次世界大戦が勃発する。
一般相対性理論
アインシュタイン自身が、「特殊相対性理論」は全てのケースをカバーしていないことを知っていた。彼は全ての場合に当てはめることのできる「一般相対性理論」の完成に腐心する。そして、二〇一四年にそれを発表する。それは、「時間だけではなく空間も歪む」という、またまた「ぶっ飛んだ」理論であった。
「太陽の近くにある星の光が、太陽の重量にゆがめられる。」
ということで、一般相対性理論は証明できると考えられた。太陽の傍を通る光は、その巨大な質量によって引き寄せられる、つまり、太陽周辺では空間に歪んでいるはずだというのである。しかし、普段は、余りにも明るい太陽の光に遮られ、それは観測できない。皆既日食が唯一のチャンスだった。
一九一九年に、次の皆既日食が起こることは分かっていたが、観測できるのは南米とアフリカの一部だけだった。第一次世界大戦中、そのような距離を移動するのは、極めて危険なことであった。幸いなことに、日食の直前に戦争は終わり、英国は、天文学者と物理学者を南米とアフリカに派遣することができた。写真に撮られた観測結果は、英国に持ち帰られ、分析されることになる。
結果は翌年発表された。一般相対性理論が予測した通り、太陽のすぐ横の星の位置が普段とずれていた。つまり、空間は歪んでいたのだ。この結果、アインシュタインは「時の人」となった。「相対性理論」は当時の流行語になったという。
合衆国へ
一九六四年、ビートルズが日本を訪れたとき、日本中大騒ぎになったが、一九二一年、アインシュタインが合衆国を訪れたときも「ロックスター」並であったとアイザクソンは書いている。アインシュタインを米国に招待したのは、シオニズムの指導者、チャイム・ヴァイツマンであった。彼にとって、時代の寵児とも呼べるアインシュタインが、ユダヤ人であることは大きな意味があった。ヴァイツマンがアインシュタインを米国に招いたのは、十分政治的な意図があったのだ。彼は沢山の大学で講演をし、講演はいつも超満員だったという。
結果的に、アインシュタインは米国が気に入り、後年、プリンストン大学から教授としての招聘を受け入れ米国に移住、米国籍を取得することになる。そして、純粋に学問の道を歩みたかったアインシュタインだが、政治への関与を余儀なくされる。
ノーベル賞
アインシュタインは、「相対性理論」と「量子論」で、自分はノーベル賞を貰えることを確信していた。彼は、ミレヴァと別れる際、
「自分がノーベル賞を受賞した際には、賞金の全てをお前に渡す。」
と約束していた。「すごい自信」と思うが、自分の理論の正しさを知っていたのは彼自身だったのだ。ともかく、離婚慰謝料を払うためにも、彼はノーベル賞が必要だったのだ。しかし、ノーベル賞はなかなか回って来なかった。反対者の理由は、
「アインシュタインの理論は実験で証明されていない。一種の哲学である。」
というものであった。しかし、一般相対性理論が、皆既日食の実験で証明された翌年の二〇二一年も、彼はノーベル賞を貰えなかった。そこには、彼がユダヤ人であるという政治的な判断があったと、アイザクソンは述べている。しかし、ノーベル賞選考委員の中に、科学は政治から独立しているべきだと主張する人もいた。一九二二年、アインシュタインは、遂にノーベル賞を受賞する。しかし、それは、「一般相対性理論」に対するものではなく、「光電効果」に対するものであった。
アインシュタインと同じ年にノーベル賞を受賞したニールス・ボーアは、彼の量子論のなかで、量子の位置は、確率でしか表現できないと主張した。しかし、アインシュタインは、量子の位置は、計算で確定できるはずだと考える。その計算式の発見が、彼が死ぬまでのライフワークになる。
「シュレーディンガーの猫」というエピソードが面白い。ボーアの言うように、量子の位置を確率でしか表現できないとすると、五十パーセントの確率で原子崩壊を起こす放射性元素と、原子崩壊が起こると青酸ガスが発射される装置と一緒に箱に入れられた、猫の生存確率は五十パーセントである。ふたを開けない限り、猫は半分死んで、半分生きているということになる。実際猫は生きているか死んでいるかでどちらかで、半分死んでいることはあり得ない。これにより、物理学者のシュレーディンガーは、ボーア等の唱える確率論の矛盾を論じた。アインシュタインも、シュレーディンガーと同じ考えであった。
しかし、アインシュタインは死ぬまで、その確率論を打ち破る理論を見つけることができなかった。
再び合衆国へ
ドイツでは、ヒトラーの率いるナチスドイツが台頭し、反ユダヤ主義が巻き起こる。多くのユダヤ人が、ドイツからの脱出を図る。五十四歳のアインシュタインは、米国、プリンストン大学の教授職を得て、一九三三年、妻と、彼女の娘と三人で、米国に渡り、プリンストンに住み始める。彼は、そこで死ぬまで住むことになる。彼と妻のエルザは、自分たちの恵まれた境遇に感謝すると同時に、ヨーロッパにいるユダヤ人の同胞を案じる。一九四〇年、アインシュタインは米国籍を取得する。
物理学者のユージン・ウィグナーは、核分裂の理論を発見、アインシュタインも、それを利用すれば、強力なエネルギーが得られることを認める。一九三九年、アインシュタインは時の大統領ルーズヴェルトに手紙を書き、原子爆弾の理論的な可能性を提言する。それを基に研究が進められ、第二次世界大戦で日本に対して原子爆弾が使用されたことは述べるまでもない。これにより、アインシュタインを、核兵器の産みの親として報じたマスコミも多かった。
しかし、基本的にアインシュタインは、リベラルな立場を貫き通した。そのため、一九五四年、マッカーシー上院議員による「赤狩り」の際は、共産主義のシンパとして批判されている。しかし、バーナード・ショー等、他の文化人が彼を擁護し、アインシュタインに対する攻撃は終息した。
アインシュタインと宗教
物理学と宗教は、相容れないものなのだろうか。アインシュタインはユダヤ人であるが、一度もシナゴーグへ行ったことはないと、自身が述べている。米国におけるユダヤ人の宗教的指導者であったコンラッド・オコネルはアインシュタインに、
「あなたは神を信じるのか、五十語以内で答えて欲しい。」
と問うた。それに対するアインシュタインの回答は、
「宗教のない科学は無力で、科学のない宗教は盲目だ。」
というものだった。彼は、自分は無神論者ではないと言っている。物理学者は「神の作った世界の調和を見つけ出す」のが役割だと彼は言う。
アインシュタインは、ユダヤ人国家の建設には余り肯定的でなかった。結果的に、イスラエルがされる。イスラエルの初代大統領のヴァイツマンが亡くなった後、アインシュタインが二代目の大統領の候補になったという。ちなみに、イスラエルでは首相が政治的な指導者で、大統領は名誉職であるとのこと。それにしても、アインシュタインが候補に挙げられた点から、ユダヤ人社会において、如何に彼が「希望の星」だったか推測される。アインシュタイン自身はそれを最初は悪い冗談だと一笑したらしいが。
死去と遺産
アインシュタインは一九五五年、動脈瘤の破裂によって亡くなる。数日前から体調の異変を訴え、医師は手術を進めたが、彼はそれを拒否した。そして、最後まで、紙に数式を書き綴っていたという。
アインシュタインの業績なしには、今日の工業技術は存在しない。原子力、半導体、レーザーからDVDに至るまで、相対性理論と、量子論が応用されている。 アインシュタインは、自分では全く実験をやっていない。あくまで、頭の中で考えたことを発表したにすぎない。言い換えれば「狂人の妄想」と言われても仕方がない世界だ。しかし、その「妄想」の多くが実験的に証明され、彼の理論が正しいことが証明される。これだけのことを「妄想」できた人物は、やはり「天才」と呼ばれるしかないと私は思った。アインシュタインの理論が身近であるというのも面白い。例えば、携帯電話。GPSの電波を発する人口衛星は、猛烈なスピードで宇宙空間を飛んでいるがゆえに、地上から見ると僅かに時間がずれる。それを携帯の機能が調整して、正しい位置情報が表示されるのである。
学校で「相対性理論」はサラッと習ったが、今回、改めて勉強する機会ができて、それも良かったと思う。そして、勉強すればするほど、アインシュタインの偉大さを知ることができた。
(2020年6月)